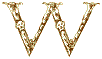
ilbur and Count Grey 2
ウィルバー少年とグレイ伯爵 2
少年は暫し伯爵の真名(まな)の力に囚われていました。強い名の力は時に、他者にまで影響を及ぼすのです。
漸く我に返った少年は、最も問いたかったことを口にしました。
「では——<死>とは?」
存外あっさりと云えたので、彼は我ながらに驚きました。そんな彼を、伯爵はさも面白いものを見るような目で見ました。
「理屈では——肉体から魂(アニマ)が抜け出すことで肉体と心(シン)の繋がりが切れ、夫々がバラバラに乖離してしまうこと。全ての源であるアニマを失った体は、その瞬間から崩れ始め、やがて形を失う」
すると、少年は今にも相手に飛び付きそうに身を乗りだします。
「眠ってもまた目が醒めるのは、アニマが抜け出さずに残るからですか?」
「解っているじゃないか!」
伯爵は嬉しそうに目を瞠りました。
「そう、人が眠っている時、シンだけがどこかへ抜け出してしまうことがある。だがアニマがあるから、再び目覚めることが出来るのだ」
この辺りには古くから論争があるがね、と彼は付け加えました。
「<死>はしばしば<眠り>に喩えられるが、それは大変理に適っていることなのだ」
伯爵は珍しく能弁でした。
「つまり人は毎日、仮の死を経ては蘇っていると云うわけだ」
「でもいつかは死ぬんです」
云った側から、少年は口元を押さえました。
とても強い言葉を口にしてしまったのです。
じわじわと、口の中に重い影が溜まります。
苦くて、甘い——
それは血の味に似ていました。
少年は椅子に背中を預けました。
「僕、知っているんです。父さまはもう……」
苦しさに、黒い睛が濡れて光ります。
「なのに、お祖父さままで……」
「まだ分からぬさ」
「分かるんです! 彼方此方に扉が開いて、」
少年は声を極限まで潜めました。
「黒い影が見張っている」
伯爵は、その整った貌に深い憂いの表情を浮かべました。
「君にはあれが見えるのか」
真なる闇で紡いだ衣を弄び、嘲笑う稀人たち。
命の炎が消えゆく時、無防備な魂を喰らわんと、その瞳を天犬の睛(シリウス)の如く燃やしつつ、そっと息を潜めている——
「目を逸らすと近付いてくる」
少年の横顔を見た伯爵は、とても古い友人のことを思い出しました。
「目を逸らすと近付いてくる」
初老の男はそう云って少し笑いました。
「だから私は見詰め続けるのだ。命の尽きるその瞬間迄ね」
「怖くはないのか」
青年は訊きました。
「怖い?」
男は瞠目しました。
「何を恐れる必要がある?」
青年は年老いた男の目の中に、無邪気な輝きを見ました。
「貴方は死すら楽しもうと云うのだね」
「当然だ。知らないことを知るのはとても楽しい」
男は笑いました。
「ただ残念なのは、それ以上何を知っても、誰にも教えてやれないことだよ」
陽気に笑う彼を、青年は少し羨ましそうに見やりました。
その紫水晶の視線に気付いた男は、友の名を呼びました。
「ヴラッド、」
青年は暗い目を伏せます。
老人は静かに云いました。
「死ぬことよりも、常に死を思うことの方が酷だ——そうだろう?」
伯爵は稀代の客人に、刺すような視線を投げました。
「目を逸らすな……あれは影だ」
「あれが?」
「そうだ。第七門の果てより来たりし、<影の女王(ノクス)>の使者」
伯爵は黒い影を見据えたまま云いました。
「だが安心し給え、彼らは既に目的を果たしたようだから」
漆黒の使者は、その胸に目映い光を抱えて、満足げに笑っていました。
「ただの通りすがりだ」
影はいつの間にか消えていました。まるで全てが夢だったかのように。
「幻みたいでした」
「そうかも知れぬ」
少年はもの問いたげな目を向けます。
伯爵はもの云いたげな目を向けます。
ふと、少年は呟くように云いました。
「毎晩寝る時、思うことがあるんです」
伯爵は無言で頷き、耳を傾けました。
「もしかしたら僕が今生きている世界は幻で、目が醒めたら別の世界なのじゃないかとか、若しくはこのまま目が醒めないのじゃないかとか、僕は本当は僕じゃないのかも知れないとか……」
少年は賢くとも、矢張り一人の子供でした。
「怖いのです。考えだすと、止まらなくて——」
「誰もが通る道だ」
伯爵は云いました。
「君のお父上も、お祖父さまも、そのまたお祖父さまも」
伯爵の言葉に、少年は顔を上げました。
「本当?」
「本当だ」
伯爵はすっかり暗くなった窓の外を見ます。闇に包まれた空に、銀の鏡が輝いていました。
「人はずっと知ろうとしてきた」
己は何者なのか。どこからやってきて、どこへ行こうというのか。
世界の何たるか。どこからはじまって、どこまで続いているのか——
「だが全てを知るには、人の命はあまりに短い」
少年はぐいと涙を拭いました。
「不死者(フィニス)は永く生きるのでは?」
「永遠に近き時を生きるが——肉体には限りがあるのだ」
その言葉に、少年は悟りました。
「でもアニマは<永遠>に続いていく?」
伯爵は満足げに微笑みます。
「そう、アニマは大いなる河の流れと同じ。流れ流れて止まることを知らない。仮に止まろうものなら、忽ち滅び去るだろう。溜められた水が淀み、やがて腐っていくように」
「では<生きる>と云うことは?」
少年の瞳が強い輝きを帯びます。伯爵は歌うように云いました。
「<感じること>だ。心を絶えず流し続けること」
「流れを止めたら?」
「深みに囚われる」
「深み?」
「……闇の深淵に沈んで、二度と浮き上がれない」
少年は心臓を氷の手で掴まれたような思いがしました。
影の燃える瞳を見詰めたときのように激しく痛みます。
(息が出来ない)
胸元を掴む少年の額に、伯爵は軽く手を触れました。
「君は心臓が悪いのだね」
少年は、自分の身体に何か暖かいものが流れ込んでくる気配を感じました。苦しさが、不思議と消えていくのです。
「あなたは……何でも知っているのですね」
「いや、私にも絶対に知り得ないものが一つだけ——」
伯爵は最後まで云わずに、白い手を離しました。
「……それではもうお暇するよ。お祖父さまに、どうかお大事にと伝えておくれ」
背を向けた伯爵を、少年はその手を引いて引き止めました。そして、自分の二倍はあろうかという背丈の彼をグイと見上げます。
「ま、また来てください! 今度はもっと勉強しておきますから」
それを聞いた伯爵は、一瞬、心から驚いた表情を見せ、目を細めました。
「ああ、また会おう。……屹度だ」
「『時は逃げ去る』、か」
赤い液体の入った瑠璃杯を片手に、銀髪の老人が云いました。
「時間は逃げないだろう」
差し向かいに座った青年が云います。
「逃げるのは人のほうだ」
痩せぎすの青年は、瑠璃杯を一気に空けました。
「うん、アルケスの葡萄酒は美味い!」
彼の痩けた頬はうっすらと赤みを帯び、お陰で普段よりも幾分健康そうに見えます。
「飲み過ぎじゃないか、ウィルバー?」
云いながら、老人も美味しそうに飲みました。それを見て、青年は上機嫌で笑います。
「こんな良い月の晩だ、飲まずにはいられない」
窓の外では、丸い銀の月が煌々と輝いています。
その輝きを身に受けながら、老人は呟きました。
「なるほど……時が経つのは、案外早いものだ」
「おや、やけに感傷的ですな、グレイ卿?」
青年は揶揄いながら伯爵を見やりました。ところが、
「ヴラッド?」
彼の黒曜石の目に映ったのは、見慣れた老人の姿ではありませんでした。月明かりに浮かんだ彼は、青年と同じ歳くらいの若者の姿をしていたのです。
二三度眼を瞬かせた青年は首を振ってみました。
「矢っ張り、一寸酔ったかも知れない」
青年の言葉に、伯爵は紫水晶の目を細めました。
「酒にか? それとも月にか?」
紺碧の空に浮かぶ月は、さながら夜気に晒された薄氷で、軽く触れただけで、粉々に砕け散ってしまいそうでした。
Crudelius est quam mori semper timere mortem.
死ぬことよりも常に死を思うことの方が残酷である。

