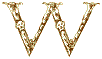
ilbur and Count Grey 1
ウィルバー少年とグレイ伯爵 1
ウィルバー少年の祖父、パテル・ヴァン=ヘイル博士は魔工学の権威で、たいそう顔の広い人でした。生前、たびたび知人を屋敷に招いては、色々なことを遅くまで話し込んだものです。
或る日、もう陽も傾きかけた頃になって、博士は一人の男を連れて帰りました。
「こちらはグレイ卿だよ。私の古い友人だ」
「君が博士のご自慢の孫息子だね?」
美しい銀色の髪を夕陽にキラキラと輝かせながら、客人は云いました。
「宜敷く」
人並み外れて背の高い彼を、少年は無言で見上げました。怖いもの知らずで名高い悪戯坊主も、この希代の客人の前では何故か、驚くほど大人しくしていました。
博士が自慢の書庫へ案内すると、伯爵は興味深そうに辺りを眺めました。長い歴史あるヘイル家が何代にも渡って集めた貴重な書物が、たくさん収められています。
ふと、一冊の書が伯爵の目を惹きました。
「これは……メルクルの『アニマ論』!」
「そうとも! いやはや、それは家宝とも云うべき一冊だ」
はっはっは、と陽気に笑った博士に、客人もつられて微笑みました。所々剥げ落ちそうな革張りの表紙に、そっと手を触れます。宵闇色の双眸が、燭台の灯りを受けて奇妙に光りました。
「彼は詩人でもあってね。今でも覚えている名句があるよ——」
三百年前の時代を生きた錬金術師のことを、彼は自分の友人のことのように話しました。そんな彼を、ウィルバー少年は不思議そうに見つめています。
不意に、伯爵の紫水晶の瞳が少年を捉えました。少年は咄嗟に身を翻し、その場を離れました。
「嫌われてしまったようだ、」
伯爵は、しかし面白そうに呟きます。
「賢い子だ」
「好奇心旺盛でな……あの歳で此処の本を読みおる」
博士は笑いかけましたが、ふと真顔で云いました。
「彼は予期しているのだろう……父親がもう長くないということを」
少年の父——博士の末子は生まれつき身体が弱く、今や殆ど寝たきりでした。
「<黒影病>と云うそうだ」
近年ミザールで猛威を振るう謎の病です。突然、身体が凍るように冷たくなったかと思えば、燃えるように熱くなり、みるみるうちに痩せ衰えて死に至る怖ろしい病でした。
「だからあなたの屋敷に?」
「それもあるが、看病疲れの母親から遠ざける為だ。母親は彼に酷く当たっていたようだから」
少年の母親は、我が子を<影に攫われた子>と信じているのです。
「あの程度の悪戯で影の子扱いとは……儂はもっと凄かったがね」
老博士は無邪気な少年のように笑い、深い溜息を吐きました。
「孤独なのだ、彼は」
そう云って、博士は客人をちらりと見遣りました。
「孤独、か」
博士の呟きは、伯爵の心に小さな波紋を残しました。
それからというもの、伯爵は毎日のように屋敷にやってきました。いつも同じ時刻——陽が傾き、夕星(ヴェスペル)が輝き出す頃に。
ウィルバー少年は、不思議な訪問者と一度言葉を交わしてみたいと思っていました。しかし彼に近付くのは何となく気が引けました。<恐怖>と云うと、少し語弊があるかも知れません。知ってはいけない秘密を探ろうとしている、そんな気持ちがしたのです。
かくして彼はいつも、僅かに開いた扉から中の様子を隙見するばかりでした。
それからしばらくのこと、博士が突然の体調不良に見舞われました。
「風邪ですかな?」
知らずにいつものように訪れた伯爵に、博士の妻は云いました。
「近頃急に寒くなりましたし……油断したのですわ」
折角お越しくださったのに、申し訳ありません、と彼女は詫びます。
「いえ、それでは——お大事にとお伝えください」
「ええ、またいらしてください、」
と云って、博士の妻は苦笑しました。
「あの人、退屈で死にそうだと申しておりますの」
すると伯爵も笑います。
「確かに、退屈は辛い」
死ぬほどに、と彼は呟くように付け加えましたが、あまりに小さな声だったので、彼女の耳には届きませんでした。
「……ではこれにて、」
そのまま帰りかけようとして、彼ははたと歩を止めました。
「ああそうだ、<小さな博士>はご在宅かな」
博士の妻が首を傾げたその時です。大階段をバタバタと駆け下りてくる音がしたと思うと、少年らしい甲高い声が響きました。
「伯爵! 待ってください!」
「ウィル、静かになさい」
博士の妻が叱ります。すると、客人は云いました。
「元気なことは良いことですよ」
思いがけない言葉に、博士の妻は驚きつつも、確かにそうですわね、と笑いました。
広い客間に、やせっぽちの少年と、背高の伯爵——二人は会話の切欠を探しながら、暫く黙りこくっていました。
少年は窓際で、暮れゆく空を見ながら。
伯爵は更紗張りの長椅子に掛けながら。
燃えるような赤い太陽が、逃げるような速さで沈んでいきます。
そしてとうとう、最後の残り火が、遠くの森の影に消えました。
「あの、」
少年が口を開きました。
「あなたは——何者なのですか?」
彼は黒曜石の瞳で、真っ直ぐに客人を見据えました。
「何者か、」
予期していた質問に、伯爵は嘲笑とも取れる笑みを浮かべました。
「君はもう分かっているだろう?」
質問を質問で返され、少年は戸惑いました。蒼ざめた貌に、黒い瞳が不安げに揺れます。
「お祖父さまを連れて行かないで……!」
「連れて行く? 一体どこへだね」
震え声の少年に、伯爵は微笑みました。そして間近にあった燭台を手に取ると、骨のような指をパチリと鳴らしました。するとどうでしょう、滑らかな白い蝋燭に、ポッと灯りが点ったのです。
(魔術師(メジャイ)だ!)
少年は咄嗟に退がって、壁にぺたりと背中を付けました。一方の伯爵はその灯火にそっと息を吹きかけます。すると、炎は命を得たように一等明るくなりました。
その時、少年は鋭く息を呑みました。部屋の壁に濃く映し出された客人の影が、異様なまでに黒々と揺らめいて、少年の心を掴んだのです。彼の黒い瞳に映ったもの——それは一対の巨きな翼でした。
「彼は大切な友人だ。何処へも連れて行きはしない」
少年は目を大きく見開いたまま、ただただその黒い影を見詰めています。屋敷中がシンと静まりかえっていました。まるで、自分と伯爵の他には誰も居ないような気さえしました。
伯爵は燭台を置きました。炎はもう小さくなっています。そしてあの翼も、見えなくなっていました。
不意に、押し黙っていた少年が口を開きました。
「あなたは、魂(アニマ)の永遠性についてどう思われますか?」
「君はどう思う?」
またもや質問で返されてしまいました。
「ええと——」
少年はグッと唇を引き結んで考え、呟くように云いました。
「果てしなく長く、たとえ永遠に感じたとしても、終わりは、必ずやってくる……」
「ではその後どうなる?」
紫水晶の睛で見つめられると、少年は息苦しささえ覚えました。何か、強い力で押し潰されてしまいそうな感じです。
「分かりません。僕には……」
可哀相なほど青ざめた少年に、伯爵は椅子を勧めました。少年はまだ考えていましたが、半ば無意識に座りました。
彼が座ったところで、伯爵は口を開きました。
「アニマとは云わば、肉体や精神を一つに繋ぐ鎖だ。この世界の生きとし生けるものは皆、アニマを持っている」
「それは識っています。『アニマこそ全ての源』だと」
少年は祖父の著書にあった言葉を借りました。
「うむ、」
伯爵は頷きましたが、その答えには不満足なようでした。
「だが、アニマだけでは不完全なのだ。肉体と、心(シン)が揃って初めて、一つの生命となる」
「では魔力(マナ)は? マナは無くても生きていられます」
「そうだ」
「この国の人々——メジャイは非能力者(デジャイ)を人だと思っていませんが」
「残念ながら」
「マナとは何なのです?」
「正確には、シンを解放したり制御する力だ」
「ではシンとは?」
「君は何と考える」
少年は俯き、記憶の海を探りました。
「僕は——」
気付くと少年は深い海の中を漂っていました。<心海>と呼ばれる、底なしの黒い海の中を。
彼は以前にもそこを訪れたことがありました。
深く深くどこまでも、ぐるぐると渦を巻く、果てしない闇の世界。
そこで<彼>に出会ったのです。
「君は誰?」
——僕は、
「どこから来たの?」
「君こそ誰なんだ?」
声は云いました。
「僕は君さ」
「君が僕?」
「そうさ」
「では僕は誰だ?」
「僕に決まっているじゃないか」
声は笑いました。
「君は考える」
「僕は考える」
「考えている時、人は独りだ」
「僕も、独りだ」
「そう誰もが独り」
「誰もが独り」
——たった、ひとり。
「それが君だよ」
少年は闇の中に幽かな光を見ました。
「そして、それが僕だ」
少年は大きく息を吸って目を開けました。
ひどい息苦しさに、今までずっと水に潜っていたような気がしました。けれども、そこは紛れもなく祖父の屋敷の中で、目の前には物知り顔の伯爵が座っているのです。
「答えは見つかったかね?」
少年は頷きます。
「シンとは——僕が……僕であるということ」
「そう、それは真名(まな)によって縛られる」
伯爵は厳かな口調で云いました。
「君が<ウィルバー>で、私が<ヴラッドメリ>であるように」
少年は驚きました。
(ヴラッドメリ)
高貴なる者は、滅多に己の真名を口にしないものでした。
まして言葉を交わしたばかりの、ちっぽけな少年になど。

